 |
1919年にイギリスのドラモンドが、オレンジ果汁から壊血病予防因子を発見し、これをビタミンCと呼ぶことを提唱しました。
ビタミンCは、十分に摂取したときに、肌のしみ、そばかすを防ぐ作用をはじめ、さまざまな働きをすることがわかってきています。「風邪にはビタミンCがよい」はすでに常識のようになっており、がんの予防としての期待も大きいようです。
ストレスが多いときにも活躍するビタミンCを十分とって、体の調子を整えましょう。
|
ビタミンCは、いろいろなところで活躍しています
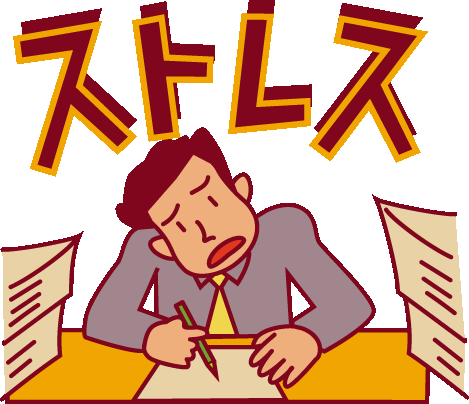 |
|
 |
|
 |
| ストレスが多いときに |
はりのある肌に |
|
貧血の人に |
|
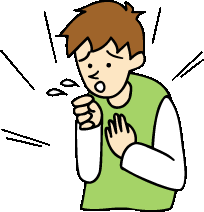 |
|
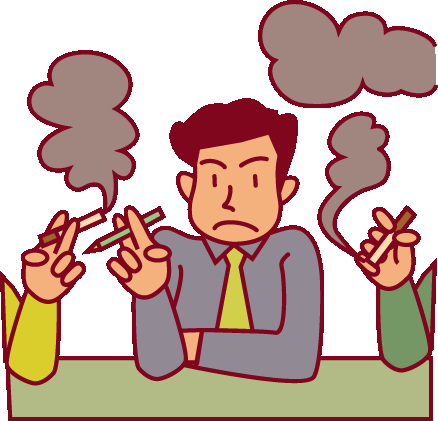 |
|
|
風邪をひいたときに |
たばこを吸う人に |
|
|
| コラーゲンの合成にビタミンCは不可欠 |
コラーゲンは体を作る全タンパク質の約30%を占め、細胞と細胞をつなぐ結合組織や骨、血管、各種器官、筋肉などを丈夫にしているタンパク質です。コラーゲンが細胞をしっかり固めれば、風邪のウイルスも容易に侵入できません。ビタミンCはアミノ酸からコラーゲンを作る時に役立っているのです。そのため、ビタミンCが不足すると肌のはりが失われ、歯茎から出血しやすくなってしまいます。
|
| 病気に対する抵抗力を高める |
血液中の白血球やリンパ球はビタミンCを多く含んでいて、それらは体の中に細菌が入ってくるのと戦います。また、自らもウイルスに攻撃をしかけるなど、攻めと守りの両面で体を守ります。抵抗力が高まれば、かぜはひきにくくなり、自然に治る力が強まります。
|
| ストレスにもビタミンC |
アドレナリン(副腎髄質ホルモン)はストレスがかかると多量に分泌され、脈拍を速めたり、血圧や血糖値を上昇させてエネルギー供給体制を整えてストレスに対抗します。このホルモンの合成にもビタミンCは欠かせません。ストレスは不安・緊張といった精神的なものだけではありません。騒音、過労、睡眠不足、寒さ、暑さも体にとってはストレスです。思っている以上にビタミンCの消耗は激しいのです。体には約1500mgのビタミンCの貯えがありますが、ストレスが多いとどんどん消費されてしまいます。ビタミンCの栄養所要量は、1日100mgですが、多めにとることを心がけましょう。
|
| ガンの予防にも期待できるとの報告あり |
肉や魚を食べるとその中のタンパク質が胃で消化される際に、アミンという物質ができます。このアミンと同時に野菜、果物、ハムなどの食肉加工食品、飲料水などに含まれている亜硝酸を摂取すると胃の中でアミンが反応してニトロソアミンが生成されます。ニトロソアミンは、発ガン性物質であることが実験的に示されているものなのです。やっかいなことに、胃以外にも腸や口腔、食道、膀胱など、体のいたるところで合成されてしまいます。ビタミンCには、このニトロソアミンの合成を食い止める働きがあることが確かめられているのです。
また、ビタミンCは、細胞間の接着剤のような働きをするコラーゲンの生成にも関係しています。コラーゲンの合成が促進すると細胞同士の緊密な結びつきが強化され、がん細胞に対抗するため、がん細胞の増殖を抑える効果があると考えられています。ちなみに、米国で多くの人が大腸がん予防のためにビタミンCを1日1000〜2000mg摂取しています。さらに、ビタミンA、Eにも、がん予防の効果があるといわれており、1種類のビタミンだけでなく、A、C、Eを組み合わせることが望ましいでしょう。
|
| 喫煙者の血液中のビタミンC濃度は低くなっている |
体のなかでは、1500mgほどのビタミンCが蓄えられ、それを超えると尿中に排泄されます。たばこを1日20本吸う人では、貯蔵される量が1000mgあるいはそれ以下に減ってしまいます。20本で500mgなので、1本につき25mgのビタミンCが消費されることになります。米国などでは喫煙者に1日200mg以上のビタミンCの摂取を勧告しています。
|
|
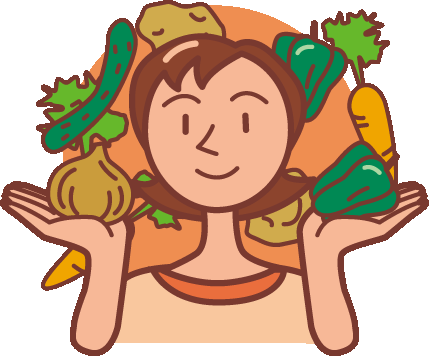 |
| ビタミンCが不足すると |
ビタミンCの働き |
風邪をひきやすい。
免疫力、解毒力が弱まる。 |
活性酸素の害を防いで老人性白内障を予防。 |
肌にはりがない。しみ、そばかすができる。
歯ぐきから出血しやすい。 |
貧血を予防。
ストレス、疲労を和らげる。 |
疲労感、脱力感。
神経の失調をおこす。 |
風邪を予防し、回復を早める。 |
| 胃がん肝臓ガンなど発ガンリスクが高まる。 |
肌にはりをもたせる。
粘膜や骨を強くする。 |
| 副腎が弱り、アレルギーが出やすい。 |
アレルギー反応を抑える。 |
骨、筋肉、胃腸が弱る。
骨折しやすい。 |
血中コレステロール値を正常にする。 |
貧血、切傷が治りにくいなどの障害が出やすい。
欠乏がひどいと壊血病になる。 |
壊血病を予防。発ガンを抑制。 |
|
|
女性のためのビタミンC |
| 貧血の人に |
貧血は思春期以降の女性に多い症状の1つで、5人に1人が貧血ともいわれています。貧血を治すには鉄分を上手に摂ることが大切です。毎日の食事からとる鉄分は植物性のものが多いのですが、植物に含まれている鉄分は体に吸収されにくいかたちで存在しています。
そこに、ビタミンCが加わると、鉄分が吸収されやすいかたちに変わるのです。ビタミンCの不足した食事にビタミンCを60mg添加すると、鉄の吸収率が約4倍に高まることがわかっています。かたちの変わった鉄分は小腸から吸収されて、赤血球に利用されて酸素を運ぶ働きをするのです。 |
|
| 更年期を乗り切るために |
| 更年期は閉経を前にして卵巣の機能が低下しはじめ、閉経するまでの期間です。閉経はホルモンの分泌のスイッチが切り替わる期間で、更年期はその準備期間といえます。女性ホルモンの中枢は脳の視床下部にあり、そこから脳下垂体に指令がでます。ここに自律神経の中枢もあり自律神経が影響を受け、いろいろな症状がでます。閉経期には副腎皮質から女性ホルモンの代わりになるホルモンが分泌されて、体の変調を少なくして、更年期を乗り越えるような仕組みがからだにはあります。副腎皮質ホルモンが働くには、ビタミンCが必要で、十分とりたいものです。 |
|
|
| 旬の野菜の方がビタミンCは多い |
現在は、味の点ではハウス栽培でも路地ものとの格差がなくなってきました。しかしながら、ビタミンの量には差があるのです。ほうれん草のビタミンC量は食品成分表では、100gあたり65mgですが、旬の11〜12月のものには約70mg、6〜7月の夏場に収穫したものは約23mgで、夏のものは冬に比べると1/3〜1/4しかありません。トマトでは食品成分表には、20mgとなっており、旬の夏のものは21mg、冬のものは15mgで、やはり旬のものの方が多くなっています。ですから旬の野菜からビタミンCをとりたいものです。
|
| 取りすぎがほぼ心配ないビタミンC |
ビタミンCは水に溶けるので」、余分にとっても体の外に流れでてしまいます。このため、取りすぎの心配はありません。保存中や料理でのロスを考えると100〜150mgと多めにとったほが良いでしょう。
|
| 手早い調理で効率よく摂取 |
ビタミンCはほとんどの野菜や果物に含まれていて、日本人は摂取量の約2/3を、野菜から摂っていると言われています。水溶性ビタミンであるビタミンCは、摂りすぎても余分なものは体外へ排出されますが、熱と水に弱いため、調理による損失を考慮する必要があります。野菜のゆで汁や煮汁にはビタミンCが溶け出しているので、スープなどにして丸ごと食べるのも有効です。いずれも「調理は短時間」を心がけましょう。
その点、生で食べられる果物は、最適なビタミンC供給源といえます。
|